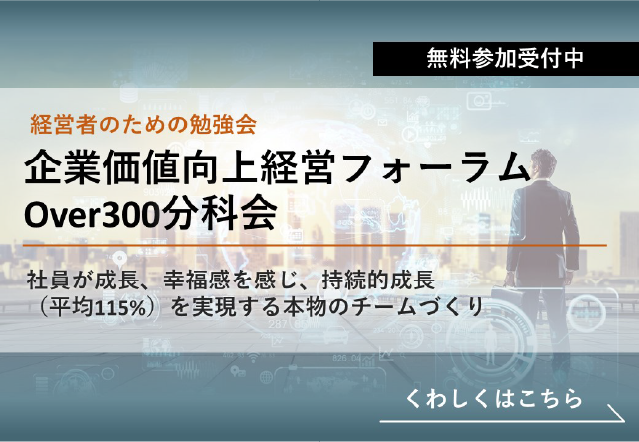ここ数日来、大変な驚きと怒りとともに世間を賑わせている2つの話題、
「大王製紙の前会長による巨額借入問題」、及び「オリンパスの損失隠し問題」。
われわれ、企業経営に関わるコンサルタントの立場でみると、
それは単なるコーポレートガバナンスの欠如という一側面の問題のみならず、
わが国の企業経営に根付く複雑かつ構造的な問題に起因する部分が大きいのではないかと考えてしまう。
もちろん、今回の2社の行為については言語道断であり、
結果的に、株主、従業員、顧客、取引先等あらゆるステークホルダーに対して、
これ以上ない裏切りと迷惑、そして損害を与えることになった。
それはいくら謝罪を積み重ねたとしても簡単に許されるものではないだろう。
しかし、それでもなお、筆者が考えてしまうのは「なぜこのような事が起こりえたのか」ということだ。
「株式会社」に対する基本的な理解の欠如またはその軽視、それを支える会社法や会計制度の穴を狙った行為、
監査法人のモラルハザード、大企業化により硬直した組織構造、そこに根付く暗黙のルール…。
2社が引き起こした問題の背景にあるこうした要因は、多くの日本企業に共通して根付く、複雑かつ多面的な問題である。
私たちはあらためて企業経営を黒子的にサポートするコンサルタントという立場を理解し、
正しく美しく成長し続ける企業づくりを目指していかなければならないと感じる。
さて、前置きが長くなったが、今回は賃貸住宅市場の現状と今度の動向について考察してみたい。
わが国の賃貸住宅市場の構造を振り返ることは、すなわち持家を推進してきた戦後の住宅政策を振り返ることに他ならない。
持家と賃貸の関係は、それこそコインの表と裏のような関係で成り立っているといえる。
■ 戦後は持家家族をターゲットにおいた住宅政策
いうまでもなく、戦後日本の住宅政策は「持家家族」をターゲットに考案されてきた。
サラリーマンの終身雇用制度の定着もあり、持家中心の政策が結果的に景気・経済対策の一環として大きな役割を担っていた。
つまり、借家住まいからマンションを購入し、いつかはそれを売却した上で、最終的には庭付き一戸建てを持つ、
といういわゆる「住宅双六」の構造を作ることにより、社会は安定し、経済は拡大してきたのである。
それらをサポートする政策として、金融制度においては、長年にわたって住宅金融公庫が持家取得を支援する為に、
長期でかつ固定型の低金利住宅ローンを提供し続けてきた。
また購入資金そのものにおいても、これまで幾度となく景気対策と銘打った後押しがあった。
こうした国をあげて持家取得を後押しする政策の結果、少なくとも過去においては借家家族より持家家族のほうが得をする環境にあったと言える。
加えて、高度成長期に生まれた「土地神話」が、さらにその傾向を後押ししていた。
1960年代以降の高度成長期に支えられた日本経済は、低金利政策の効果もあり、極めて理想的に制御されたインフレが長年にわたって続いていた。
更に、人口・世帯数が増加し、近代化の流れの中で都市に人が流入する動きも加速し、
実物資産である土地や不動産に旺盛な資金需要が集中していったのである。
その結果として「土地神話」が生まれた。
■ なぜ今の賃貸住宅は供給過多で、持家に比べ狭く小さいのか?
しかし、これは同時に、この時期に借家市場の整備が整わなかったことも意味する。
賃貸住宅市場の課題や問題点を考える上で避けて通れないテーマの1つに旧「借地借家法」の存在が挙げられる。
旧来の「借地借家法」の下では、基本的に一度借主に土地や住宅を貸した場合、貸主側の事情では「更新の拒絶」が極めて難しい制度となっていた。つまり一度貸すとなかなか戻ってこないというリスクを常に貸主側が抱える制度であったということだ。
1991年の法改正で「定期借地」が、1999年には「定期借家」が導入され、期限を区切った定期契約が可能となった。
しかし、この制度は既存の契約には適用されず、今でも旧来の「借地借家法」の下での賃貸借契約の方が圧倒的に多いという実態がある。
他方で、かつて大都市周辺で世帯数の増加が続いた時期に、近郊の農家を中心しとした地主は、
所得税対策、相続税対策、固定資産税対策として、借入による「アパート建築」の流れが拡大し、一気に賃貸住宅が増大した。
実はこの持家政策が浸透する時代背景の中で、旧来の「借地借家法」に基づいた「アパート経営の拡大」が、
今の賃貸住宅市場の諸処の問題につながっている。
すなわち、約19%という過去最悪の空家率(2008年の住宅・土地統計調査による賃貸用住宅の空家率)、
ファミリー向け貸家の供給不足、持ち家と比較した際の部屋の面積の狭さといった、
現在の賃貸住宅市場が抱える構造的な課題の枠組みを作ってしまったのだ。
■ 旧「借地借家法」下でのアパート経営者の合理的選択
まず現在の賃貸市場における「供給過多」の現状は、先にあげた土地持ちオーナーの節税対策、税制優遇によるインセンティブが大きい。
特に大都市周辺の市街化区域の農地については、当時「宅地並み課税」の導入によって固定資産税評価が厳しくなってきたという背景が挙げられる。
「宅地並み課税」とは、それまで特例として優遇されてきた農地の固定資産税評価を、宅地と農地の税の不均衡を修整するという名目で
、1972年度分から市街化調整区域の農地については、その状況が類似する宅地の価格に比準して評価されるようになった。
これは当然ながら相続税についても影響を及ぼす。
土地のまま相続する場合、この高くなった評価額すべてに対して課税されるのに対し、
借入金でアパートを建てれば、収入は減価償却や借入金利と相殺されるため、所得税はほとんどかからない。
その上、土地の固定資産税・相続税においても、小規模住宅の敷地としての軽減措置が受けられるという、
まさに土地持ちオーナーにとっては「濡れ手で粟」であったのである。
そして、物件の多くが1部屋あたりの面積が狭く1K、2Kといった小さな間取りが中心であったという理由も、
単に建築コストを抑えたいという事情だけではない。
旧来の「借地借家法」の事情を踏まえると、その根本的な背景が理解できる。
面積が狭く、少ない間取りの部屋であれば、それはやがて入居者が結婚し、
更には子供が生まれるといった新たなイベントが発生すると明らかに手狭になってしまい住み替え需要が促進される。
旧「借地借家法」下の貸主にとって、リスクであった退去の事由が貸主側から自然に生まれるのである。
加えて借主側にも前述の「住宅双六」の常識が頭に刷り込まれている為、
次なるステージ(分譲マンションまたは戸建の購入)を求めるインセンティブもそこには働いていたはずだ。
付け加えれば、頻繁に借主が変るとその度にオーナーには「礼金」が入る。
また、「土地神話」と言われるような右肩あがりの経済状況下においては、借主の変更の際に「家賃の値上げ」も可能となる。
まさにこれらの点が、当時の「アパート経営」のビジネスモデルにおけるKFS(Key Factor for Success=成功要因)だったのである。
このような背景が、賃貸住宅の過剰供給と質の低下を招いたということだ。
しかし、それはまた当時の経済状況、法制度、社会情勢からみて、
アパートのオーナーにとっては極めて合理的な選択の結果であったということも言えるのである。
■ 賃貸住宅の位置づけの変化。ファミリー向け賃貸、コンセプト重視型賃貸にチャンスあり!
他方、ここ数年、わが国における賃貸住宅の位置づけが少しずつではあるが変化している。
賃貸のフローの動きを着工数ベースでみると、未だ持家の数には及ばないものの、新設住宅着工数に占める賃貸住宅の割合は、実は増加傾向にある。そして、中でも興味深い点としては、「戸建賃貸」の着工数がここ数年急速に増えているということだ。
前述の以前までのマクロ経済環境と現在とを比較すればその要因は容易に想像できる。
長引くデフレ経済のもと、住宅地価は20年連続の下落。「土地神話」の真逆、すなわち「住宅地は値上がりしないもの」との認識が広まりつつある。そうなれば、自然と「賃貸永住思考」を持つ人たちも増えてくる。
こうした背景があり、戸建賃貸の着工が増えているのだ。
そのことが、従来の賃貸住宅市場が抱えていたバリエーションの少なさや狭さなどの問題を解決してくれるだろう。
そうすると、今後の賃貸住宅市場には捉え方によっては大きなチャンスが存在しうるといえるだろう。
第一に、ファミリーを対象とした広めの賃貸住宅に対するニーズだ。
日本の住宅は欧米から「うさぎ小屋」と揶揄されるほど、小さいというイメージがある。
しかし、こと持家について言えば、欧米との平均面積で比較した調査報告によると、それほど大きな違いはない。
他方、借家の戸あたり面積は欧米と比較するとかなり狭い。
ライフスタイルが多様化し、自由に住み替えができる賃貸の優位性が顕在化し始めてきた今、この課題は直近のニーズとしてすぐに対応していきたいところだ。
ターゲットをファミリー層にチェンジした賃貸住宅を想定すると、
商品(ハード面)、価格、プロモーション、契約の期間、入居者に対する付加サービス、出来るだけ長く住み続けてもらうためのマーケティング施策等々、
商品開発から、リーシング手法、管理手法にいたるまで、ビジネスモデルの根幹そのものを大きく変革させる必要があるだろう。
また、これまで消極的な理由(手狭になった為、致し方なく等)により退去が促進されてきたという過去のモデルから、
自らのライフスタイルに合わせて積極的に住処のバリエーションを変えていくという人々を対象とした、
特徴的で魅力ある「コンセプト重視型賃貸住宅」の開発が必要不可欠であるといえる。
戸建賃貸にせよ、コンセプト重視型賃貸住宅せよ、その根幹にはこれまでのわが国における住宅に占める賃貸の役割、ポジショニングに対する変革を起こすという考え方が必要だ。
いわゆる「賃貸は持家取得までの一時的な仮の住まい」というポジションから、「ライフスタイルに合わせて住み替える賃貸」「長く住める賃貸」というように、積極的に賃貸を選んでもらえるように、過去からの役割を変えるイノベーションが必要だということだ。
他方、忘れてはならないのが、現在既に賃貸住宅として存在するものの、中々入居の付き手がないような、
立地の優位性が低く古い賃貸住宅に対する対応である。
これらは都市政策、税制といったマクロ的な政策対応での過程に頼らざるを得ない面も大きい。
もちろん個別の事案においては、一定の投資をかけてニーズに合った住宅へリノベーションするという方法も十分に検討できる。
しかし、立地条件においても、オーナーの資金余力においても、そのような対策を打てる物件は少ないのが現状だ。
またこれは、日本全体の都市の再開発と、人口が持続的に減少する事を前提とした「コンパクト・シティー」の構想に依存する面も大きい。
日本の資産でもある自らの土地を、最も効率的に利用することを阻害する規制や保護政策は原則撤廃するなど、
明らかに供給過多状態にある日本の住宅市場における政策転換も求められている。
その意味において、官民一体となった市場ルールの大胆な改革が必要だと言える。
換言すれば、今後、このような変化に対応できない不動産オーナー、賃貸仲介管理会社は益々厳しい環境に晒されるだろう。
「変化に対応できる企業が勝ち残る――」。
あまりにも使い古された言葉ではあるが、賃貸住宅市場においても、特にこの言葉が重要な時代になったと言えるのではないだろうか。
(出典:ダイヤモンド・オンライン)