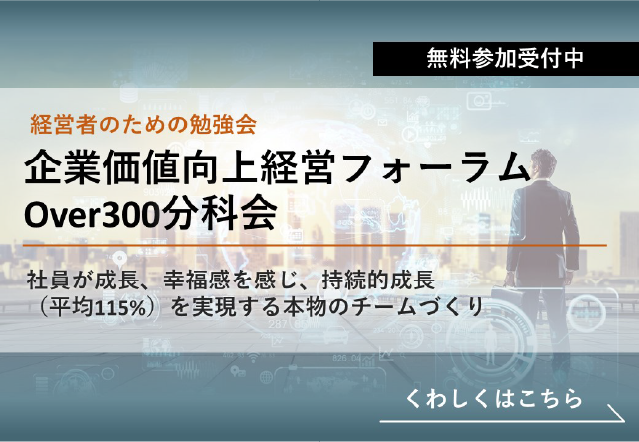■ なぜ、証拠改竄事件は起こったのか?
「郵便不正事件 厚生労働省・村木元局長に無罪判決」
このニュースとほぼ同時に、大阪地検特捜部の主任検事が証拠品であったフロッピーディスクの内容を改竄した容疑で逮捕、というニュースが流れました。その後、上司である特捜部副部長と特捜部長が逮捕されて取り調べ中というのは皆さんもご承知の通りです。
この証拠改竄事件の大まかな概要は、証拠品として押収したフロッピーディスクに保存されていた書類の作成日時が、検察捜査のシナリオ(村木元局長の指示のもとに部下が書類を作成)と合わない為、主任検事が意図的に作成日時を書き換えてしまった、さらに、その報告を受けた上司(特捜部副部長および特捜部長)が不正を気づいていながら適切な対応をしなかったのではないか、というものです。
村木元局長の身になって考えてみると、実に恐ろしい話です。
自分自身は何の罪も犯していないのに、検察で自分自身を有罪に追い込むストーリーが出来上がっており、そのストーリーに沿った供述調書が作成され、ストーリーに沿った証拠が捏造されている、といったことが行なわれているとしたら…。
そもそも検察とは、罪を犯してしまった人が「どうして罪を犯したのか」「どうやって罪を実行したのか」を明らかにした上で適正な償いを受けてもらうために、国民からは“正義の番人”としての役割を期待されている組織です。恐らく容疑者として逮捕されている3名も、もともとはそういった高い志を抱いて検察官になったのではないでしょうか。
だとすると、なぜこのような事態に至ってしまったのでしょうか。
どうしても私たちは、事件を起こした人、すなわち“個人”の方に注目してしまいます。また私たちは結果として、最終的には“個人”の責任として事態が収拾されるケースを数多く見てきましたが、どちらかといえば“組織”に着目すべき問題なのではないでしょうか。
■ “組織”に存在する“評価”のジレンマ
この事件は、検察という“組織”で起こった事件ですが、様々なビジネスに携わっている私たちも、大なり小なり会社という“組織”に属している人がほとんどでしょう。
多くの“組織”は、その“組織”のトップを頂点とした階層構造によって構成されており、その階層を昇っていくための指標として“評価”というものが存在します。
今回は、この“評価”について考えてみましょう。
証拠改竄事件のマスコミ報道から伝わってくるのは、前田主任検事はかなり優秀な検察官だということです。難しい事件であったとしても、決定的な容疑者の供述を得て解決してきた実績から、「特捜のエース」といった呼ばれ方もしていたとのこと。
検察の詳細な評価の仕組みはわかりませんが、これらの報道からは、起訴に持ち込んだ案件、その案件で有罪に追い込んだ実績などが評価を左右しているとも考えられます。また、ロッキード事件のような大掛かりな事件を手掛けたかどうか、といったものもあるかも知れません。
もしかすると、大阪地検特捜部が描いた郵便不正事件のゴールは、一連の仕組みのなかで不正な利益を得ていた部分までを明らかにすることであったとも考えられます。だとすれば、当然大きな評価を得られる案件だったかも知れません。
仮に、検察“組織”が少々おかしな状態になっていたとして、そこに“評価”という「本質的に正しいこと(証拠が揃わない容疑者を解放すること)」と「評価されること」のジレンマが存在していたのだとしたら、これほど残念なことはありませんし、早急に改善してもらいたいと思います。
■ 「人は“評価”されるようにしか動かない」
“組織”において、「人は“評価”されるように動く」、少しネガティブな言い回しになると「人は“評価”されるようにしか動かない」とも言われるように、どういった仕組みで“評価”をするのかは非常に重要です。
例えば、“会社”においても“評価”を気にするあまりに、陥ってしまうジレンマが存在します。
さらなる会社の成長を確固たるものにすべく、中期経営計画を策定した上場企業のA社。その計画では成長に必要不可欠な投資も当然織り込まれていました。
しかしながら、その中期経営計画の実行初年度、上場企業としての株主からのプレッシャーに晒されているA社は、その投資計画(開発投資や人材採用等)を見送ります。
A社は、キャッシュフローに問題を抱えているわけでもなく、計画通り実行したからといって赤字に転落することもなかったのですが、短期利益(単年度の業績の見栄え)と長期利益(将来の成長を見据えた投資)のジレンマの中、短期利益を選んでしまったのです。
今や上場企業は、四半期単位で業績を開示することを義務づけられているため、どうしても短期志向に陥りがちです。しかも、多くの市場は成熟市場になっていることから、短期利益と長期利益を同時に両立することが困難になってきており、このようなジレンマが必ずあることを認識しながら正しい意思決定をすることが求められています。
特に、(オーナー経営者ではなく)熾烈な出世競争を勝ち抜き代表取締役社長の座についているトップの方々は「限られた任期」の中での評価を得ることが、ややもすると目的化してしまう宿命を背負っています。そのため、ジレンマと戦う精神力はもちろんですが、取締役会と一体となった経営体制を築き上げることが不可欠になってきています。
また、“会社”は様々な役割を“部門”で分担しており、その“部門”にも同じようにジレンマは存在します。
“部門”のなかでも“会社”の売上を任されている営業部を例に上げてみましょう。
かつて営業部長は、部門の売上で評価されるケースがほとんどでしたが、現在では売上の他に、粗利、管理会計上の営業利益、といった数字まで評価項目に入るケースが増えてきました。
なかでも営業利益が重視される場合、売上を上げることが以前よりも難しくなってきていることから、営業部長が経費削減を気にするようになります。すると、構成比の高い人件費をコントロールしようとして新たな採用を控えたり、営業サポート業務のパート人員を減らしたり、といった施策を実行します。
ところがこういった施策は、一方で“組織”の成長を鈍化させる、営業スタッフに大きな負荷をかけて生産性を低下させる、といったデメリットも大きいことは言うまでもありません。
そういったジレンマに陥った営業部長が、次年度の予算策定会議で発表しがちなのは、
「来年も厳しい状況が予想されるため、売上目標は今年度対比100%(つまり同額)、何とか経費面を切り詰めて営業利益を105%にします」というような内容です。
「わが社は当面成長しません」という計画を耳にする若手社員のモチベーションが心配になります。
■ 「ロスを出せ!」でジレンマを打破した成城石井
以前TVでも取り上げられていましたが、食品スーパーの成城石井にかつて大久保社長(現在は相談役)が就任されたとき、店長の評価は店舗の業績によって測られていたようです。
業績悪化で利益が半減するという事態に陥っていた同社の経営改善を託された大久保社長が現場を見て回ると、どうしても品揃えの薄さが気になったとのこと。店長は利益が気になるため、極力ロスを出さないような商品の発注をしていて、その結果品揃えが薄くなり魅力のない売り場になってしまい、販売機会を損失してしまうという悪循環を招いていたわけです。
そこで大久保社長は、
「ロスを出せ!」
「目先の売上を気にしなくても良い!」
という方針を出し、それを徹底するために業績面の人事評価はほとんど無くしました。代わりに重視したのが覆面調査による“挨拶”と“接客”です。
結果として、成城石井は大きなリストラをすることもなく、組織、売り場を変えることで、利益を3倍以上に伸ばしました。組織が陥ってしまっていたジレンマを打破するために、大久保社長が具体的な方針を出し、社員全員が「お客さまに喜んでいただく為にどうすれば良いか」という本質的な課題に取り組めるようになった好事例だと思います。
■ シンプルな問いかけに答えがある
このように、“評価”の仕組みをどうつくるのかというのは、“組織”をどの方向に向かせていくのかという視点で考えると非常に重要です。
少し単純に考えてみてください。
「もっと売上(利益)を上げるために、どうしたら良いと思う?」
と社員に問いかけたときに、どんな答が返ってくるでしょうか。
一方で、
「もっとお客さまに喜んでもらうために、どうしたら良いと思う?」
と問いかけるとどうでしょうか。
恐らく、前者は一生懸命考えてもなかなか良い考えが浮かんでこないことが予想されますが、後者は、様々なアイディアがどんどん出てきます。また、それと同時に、それらの視点を“評価”の仕組みに活かしていくことで、ジレンマを感じることの少ない“組織”を構築することが可能になるのではないでしょうか。
さて、では検察に置き換えるとどうでしょう。
「もっと起訴案件を増やすために…」というのではなく、「もっと国民に安心と信頼を提供するために…」と問いかける姿勢が重要でしょう。
かつて木村拓哉さんが「HERO」というドラマで検察官を演じており、そのドラマが大ヒットした理由は、「ひとつひとつ事実を積み上げながら、真実を追究する姿勢」でした。
今回の事件を組織再構築のきっかけとして、失われた信頼を取り戻して欲しい、と多くの国民は願っているのではないかと思います。