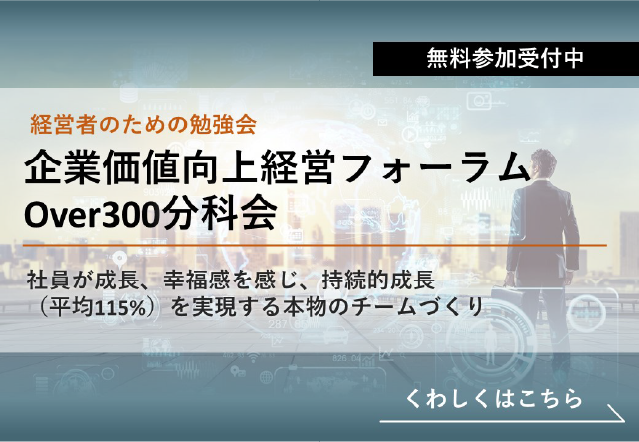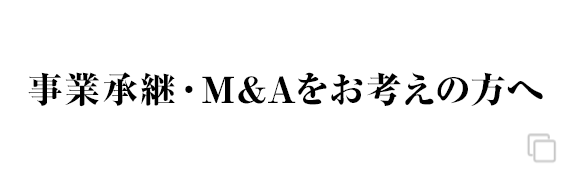■ 100万部突破の「sweet」を筆頭に、ヒットを連発
「出版不況」「雑誌不況」と言われるようになって久しいなか、「そんなことはどこ吹く風」といった勢いで躍進を続けている企業があります。それが宝島社です。
最近はメディアに取り上げられることが増えてきているので、ご存知の方も多いかもしれませんが、今や女性ファッション誌No.1である同社の「sweet」の発行部数は100万部を超えています。
現在、小学館の「CanCan」、集英社の「non-no」、光文社の「JJ」といったいずれも一時代を牽引してきたその他の女性誌が苦戦を強いられていることからも、「sweet」の100万部という数字がいかに驚異的であるか、おわかりでしょう。
さらに驚くべきなのは、宝島社から発行されているその他の雑誌についても、非常に高い確率で発行部数を増加させているということです。
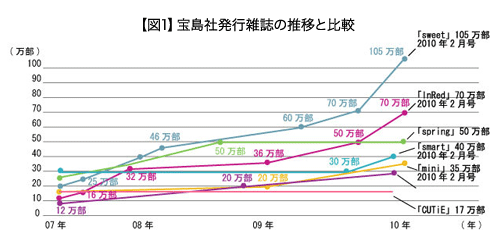
出版業界全体の市場は1996年をピークに約25%減少しており、多くの企業が業績悪化に苦しんでいます。宝島社においても、売上高は2003年の約220億円から減少し続けて、2007年度は140億円を割るところまで落ち込んでいました。しかし、そこから2008年度:約160億円、2009年度:約207億円、と低迷する市場の中で飛躍的な伸びを示しています。一体、どのような戦略によって、売上を驚異的に回復させることができたのでしょうか。
■ トップの決断“一番誌戦略”を成功させた「マーケティング会議」の秘密
宝島社の業績が悪化している最中、同社の蓮見社長が掲げたのが“一番誌戦略”です。
当時、雑誌の広告市場は次第に厳しさを増しており、宝島社も利益確保のために人件費や宣伝費などの経費削減に走っていたといいます。
そんな中、蓮見社長は広告営業の「これからは一番売れている雑誌でなければ広告が集まらない時代になる」といった声を聞き、「だったら、一番を取ろう」と打ち出したのが“一番誌戦略”です。
そして、これを掛け声だけで終わらせないために「マーケティング会議」を導入しました。これは、編集、営業、広告、広報といった各部門の責任者に社長も加わって行われる会議で、2007年の春から実施されはじめました。
これは、前例のない会議スタイルであり、「マーケティング」という言葉だけが先行して、当初は「本当に機能するのか」すら危ぶまれた状況でした。しかし、その心配をよそに会議は順調に行われ、次第に“一番誌戦略”を各部門共通の目標として認識できるようになっていきました。
やはり、編集は「人気のページをどれだけ作っていけるか」を重要視していますし、広告は「広告売上を増やしたい」、営業は「実売率を高めるためのアクションに注力したい」といったように、どうしても部門ごとに「目標のズレ」があります。
出版社に限らず、必ず存在する部門間の「対立」。放置すれば、営業は「自分たちは精一杯頑張っているが、雑誌そのものが面白くなければ売れないよ」と言うでしょうし、編集は「雑誌自体は競合と比べても大きく劣っている訳ではないから、営業の力が不足しているのでは」と他部門への不満を言うようになります。
それに対して宝島社は、社長も出席する「マーケティング会議」という場をつくって、放っておくとどうしてもズレてしまう目標を、“一番誌戦略”という共通の目標に集中させました。
また、具体的なアクションとして、広告営業に編集が同行して、ともに広告営業に取り組むといった方策を実行するなどしていきました。こうした議論の中で「必要だ」と合意したものを次々に行っていく雰囲気は、社長の決断力によって後押しされ、それが売上回復への重要な要因になったと考えられます。
■ 「付録は本物志向」「ターゲットは絞らない」…“本当に実行に移す風土”から湧き出るアイディア
今でこそ多くの雑誌に取り入れられている「上段12センチメートルの法則」。コンビニエンスストア等の本棚では表紙の上部しか見えていないことから、表紙を飾るモデル、雑誌の価格、付録等の大切な情報は、たとえ雑誌名が隠れてしまおうとも「上段12センチメートル」でしっかりと訴求することを意味しています。
また、従来の業界常識からはなかなか出てこないと思われる「値下げ」。業界としては、原価を積み上げ、必要な利益を上乗せすることが常識であり、結果として販売部数が出ない方が価格は高くなるのが当然だと思われていました。
創刊時に980円だった同社の「InRed」。当時、約12万部売れていたのですが、一番誌ではないことから広告営業は苦戦していました。そこで、マーケティング会議で、一番誌になるために価格引下げが決定。2007年9月号で700円を切る価格まで下げて勝負したところ、一気に部数は3倍になり、さらに現在では70万部を発行する雑誌にまで成長しました。
現在は、「内容が違えば、ボリュームも付録も変わるのだから、価格が変動して当然」という考え方で、毎月価格を検討しているということです。
そして今や同社最大の特長とも言われる「付録」。従来の“おまけ”の域を大きく上回る価値の高いものを提供する同社の「付録戦略」成功の秘訣は何なのでしょうか。
ブランドからのオファーにそのまま身を委ねると、コンセプトが乱れてしまうことから、編集部門が“連載ページのひとつ”という感覚で、企画から製品化までとことん関わっているとのこと。次々に大ヒット付録が生まれる背景には、徹底したこだわりがあります。
「マーケティング会議」により生み出されてきたこれらの方策には、「雑誌は顧客を囲い込みすることなどできない」という宝島社の考え方がベースにあるのではないかと思います。
「競合は、決して他の雑誌ではない」
「読者アンケートは、結果として受け止めるだけで参考にはしない」
「今、読んでいただいている人以外をターゲットとして考える」
「TVコマーシャルは全く読んでもらってない層に訴求できる番組に打つ」
確かに、何にお金を使うのかはその時々の消費者の判断ですから、「単に雑誌が競合ではない」ということには頷けます。常に新しい読者を獲得することができなければ、部数の拡大は覚束ないものになってしまうでしょう。
上記のような既存の読者層にこだわらない考えを持ってしまうと、実行する方策において迷いが生じるケースが他社などでは数多くあったように思います。しかし宝島社は「より雑誌の魅力、価値を高めるためにやるべきことをやる」という信念を貫いているところが、既存と新規の読者の支持につながっているのかもしれません。
作り手としては、ターゲットを絞り込むことでどんな内容にするのかがイメージしやすくなるため、特に女性誌では年齢や職業でターゲティングする発想になりがちなのです。そうしたなか、宝島社の「sweet」は「一生女の子宣言!」というコンセプトで「今、何歳であろうが、女の子であり続けたい」と願う女性をターゲットとしています。
この“絞り込まない”ターゲティングも、従来の枠に捉われずに柔軟な発想で臨むというスタンスの表れであり、100万部を可能にしたマーケティングの軸だとも考えられます。
■ 思わず雑誌を売りたくなってしまう書店応援キャンペーン
「書店スタッフの協力がなくては、とても達成できないと感じた」
これは、2009年にさらなる「sweet」の拡販を考えていた営業担当者の言葉です。
2009年4月に書店や取次店の担当者を招待して印刷工場見学を実施。キャンペーン等で宝島社がインセンティブを出しても通常は縁のない店頭スタッフを招待しました。
高級車ハマーのリムジンを移動に使い、印刷工場で雑誌ができるまでの工程を見学、そして編集長のトークショーなどを行い、大いに盛り上がったようです。
さらに2010年8月には、主に地方の書店スタッフを招待してのバスツアーを企画。雑誌のイメージでラッピングされたバスに乗って、都心の最先端スポットを回りながら編集長とも話ができるというこの企画も大好評を博します。
「書店スタッフに雑誌を見てもらい、お客さまにおすすめしてもらいたい」という目的で開催されたこれらのイベントは、招待した方はもちろん、実際に参加していない方々にも当然口コミで広がったため、販売の増加にも確実につながっているようです。
この話を聞きながら感じたのは、イベントに関わっている宝島社の社員の皆さんが、「招待した皆さんを楽しませたい」と心から思っていたということです。
一見、潤沢な予算を投入しているようにも見えますが、限られた予算の中で、自分たちの思いに共感してくれる方々の協力を得ながら実現にこぎつけた、というのが実態だといいます。
そういう本気の思いだからこそ、伝わる力が強くなるということなのでしょう。
■ 強みを活かしつつ、新たな市場をつくる「チャレンジを続ける風土」が鍵に
同社は雑誌以外でも、さまざまな取り組みが成果を上げています。
2010年の7月に「スッキリ美顔ローラー」(税込2980円)を雑誌の体裁にして書店で発売したところ、初版30万部が早々に完売し、さらに30万部の重版が決定しました。
また、かつて「イヴ・サンローラン」で100万部を売り切ったブランドムックで、「kitson」(税込980円)を発売し、初版120万部を展開しました。
その他、音楽CDや名作DVDなど、雑誌や書籍以外の商品を書店で販売する企画を矢継ぎ早に打ち出しており、これらの成果も非常に興味深いところです。
アップルから「iPad」が発売され、電子書籍化の流れが進むなかで、出版業界の今後はさらに厳しいものになるという見方が主流です。しかし一方で、宝島社の取り組みをみていると、日本の出版流通ほど効率の良い流通組織はない、といった見方もできます。
今後、大きな鍵となるのは、「強い部分をいかに活用しながら新たな市場を生み出していけるか」。おそらく、他業界のビジネスのなかでも、宝島社の取り組みから学ぶべき点が多々あるのではないでしょうか。